ウィーン
僕は、本屋に入った。
読書が好きな僕は仕事が終わった後、本屋に立ち寄る。僕にとって本屋はディズニーランドのような夢の場所である。
そして、僕はいつも同じ本屋に立ち寄る。橋本書店という個人でやっている店だ。
ここは、雑誌や話題の漫画、小説だけでなく、マニアックなことを取り上げた雑誌や一部のマニアに人気な小説なども置いてあり、僕の好奇心をくすぐるようなものが置いてある。
大手チェーン店ほど店は広くはないのだが、品揃えは劣っていないと僕は思う。
そんな中、僕はある本が目に留まった。
「あれは、伝説の本!」
僕は、思わず口に出してしまった。運良くこの独り言は誰にも聞かれていない。
そうだ。そこにあったのはかの有名なアンディ・ロマーノが書いた小説『消せないミートソース』である。
ロマーノは1899年にアメリカで生まれ、コックの傍ら小説を執筆していた。
彼の得意料理はミートスパゲティで、彼の働いているレストランでは好評だったらしい。
しかし、そのスパを作る際、どうしてもコックコートにミートソースがついてしまうので、あまり作りたくないと思っていた。それに、ミートスパゲティが好評すぎてそれしかオーダーが入らなくなり他の料理も作りたかったのに作らせてもらえなかったらしい。
彼は、このミートスパゲティ地獄を抜け出すためにレストランを辞め、専業小説家になった。彼は、ミートソースから着想し『消せないミートソース』を執筆し、大ヒットした。
そして、ミートソースのおかげで有名になりミートソース作家という異名がついたのだとか。
その本がなぜ伝説になったかというと初めてホラー小説にミートソースを洗濯しても落ちないという日常の悩みを取り入れたから。
これで、主婦層と料理界から支持を得たらしい。しかし、その後ロマーノはミートソース作家と呼ばれるのが嫌になって、本の絶版を要求したのである。
なので、本来はないはずなのである。
なぜ、あるのか。不思議でしょうがない。
そこで考えていると、後ろから「お客様も伝説の本に興味があるんですか?」と声がした。
振り返ると、僕より少し年上っぽい眼鏡をかけた女性が立っていた。
急に話しかけられたので、僕はしどろもどろになり、
「あ、はい……。」としか言えなかった。
女性はそれを気にしていないのか話し始める。
「私もこの本のことは前から知っていたんですが、三か月前に、この本を置いてくれって四十代くらいの外国人の方に言われました。」
置いてくれと頼まれただと! そうなると、置いてくれといった理由も気になるがなぜその人がロマーノの本を持っていたのか気になる。僕は、少し興奮気味に、
「そうなんですか? もしかして、その方ってロマーノの親戚の方とかですかね。」と聞いてみた。
「いえ、ロマーノの親戚ではなかったです。」
彼女はそう答えた。
「その方にどうしてこの本を置いてほしいんですかって聞いたんですよ。そしたら、彼はオーストリア出身で20代で日本にやってきたんだそうで、ロマーノの大ファンだって言っていました。
『消せないミートソース』は子どもの頃に親からもらったらしいんです。」
「子どもの頃から持っていた本を置いてくれって頼んだんですか?」
「いえ、その本、お酒で酔って破り捨てたらしいです。酔うと断捨離したくなるみたいで……。
いや、好きな本酔って破り捨てるなよ……。僕は彼に呆れてしまう。
「でも、彼は捨てる前に何度も読んでいたから内容を丸暗記してたんです。それで、この本が誰にも知られないままなのはもったいないと思い、パソコンで文字を起こし、印刷屋で製本して、近所の個人でやっている本屋に置いてくれと頼みまわっているそうなんです。」
「すごいですね……。」
すごすぎる。好きな本が絶版になっても、落胆するか、行動的であっても、出版社に抗議を出したりするくらいだ。しかし、自分で思い出し、文字にして、本にして書店に置いてくれと頼むなんてよっぽど自分の好きな本を読んでもらいたいんだと思った。熱狂的だ。
「店長に確認とったら置いてもOKって言われたのでここに置かせてもらってます。」
「そうなんですね。あの、ちょっと手に取って読んでもいいですか?」
「いいですよ。」
僕は少し立ち読みさせてもらうことにした。
「すっごい!」
「私、置く前に店長に本を預かってしまってまだ読んでないんですよね。フフフ。やはりすごいですか?」
「ええ、すごく誤字脱字だらけです!」
文字に起こした外国人の誤字脱字まで伝説級であった。
※これはフィクションです。こちらに登場する人物・書名は架空であり、実際の人物・団体とは一切関係ありません。
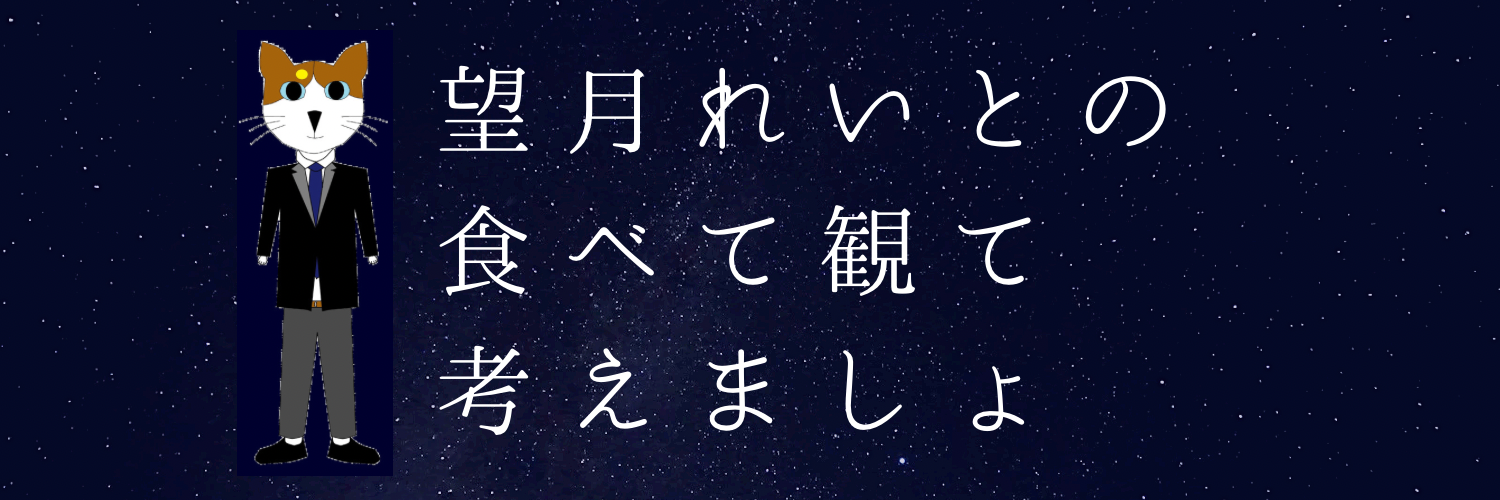


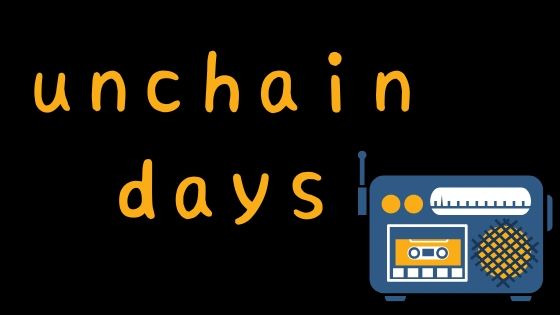
コメント